グラフの色選び完全ガイド!見やすい・伝わる配色テクニックを徹底解説

レポートやプレゼンテーションでグラフを作成したとき、「なんだか見づらいな…」「伝えたいことがうまく伝わらない…」と感じた経験はありませんか?その原因、もしかしたら「色」の選び方にあるかもしれません。
色は、情報を視覚的に分かりやすく伝え、見る人の印象を大きく左右する重要な要素です。適切な色を選ぶだけで、グラフの説得力は劇的に向上します。
この記事では、グラフの色選びに自信がない方でも、すぐに実践できる基本的なルールから、目的別の応用テクニックまで、分かりやすく解説していきます。色を味方につけて、あなたの作成するグラフをワンランクアップさせましょう!
この記事の内容(目次)
なぜグラフの色選びは重要なのか?
そもそも、なぜグラフの色を意識する必要があるのでしょうか?その理由は大きく3つあります。
情報の伝わりやすさが劇的に変わる
適切な配色は、データの関係性や傾向を直感的に理解させることができます。例えば、売上が伸びている部分を暖色系の目立つ色に、そうでない部分を寒色系の落ち着いた色にするだけで、見る人は瞬時に重要なポイントを把握できます。視線を誘導し、重要なポイントを強調できる
色は、人の視線を自然に誘導する力を持っています。グラフの中で最も注目してほしいデータにアクセントとなる色を使うことで、「ここが重要です」というメッセージを無言で伝えることができるのです。プレゼンや資料全体の印象を左右する
統一感のある美しい配色のグラフは、それだけで資料全体のクオリティを高く見せ、信頼性を向上させます。逆に、色がバラバラでまとまりのないグラフは、内容が良くても「素人っぽい」「分かりにくい」という印象を与えてしまいかねません。
【基本のキ】これだけは押さえたい配色の3つのルール
「センスがないから色選びは苦手…」という方もご安心ください。基本的なルールを押さえるだけで、誰でも見やすい配色が可能です。まずはこの3つのルールから始めてみましょう。
ルール1:使う色は「3色」を基本にする
情報を分かりやすく整理するため、グラフに使う色はベースカラー、メインカラー、アクセントカラーの3色を基本に考えましょう。
ベースカラー (70%): 背景や余白など、グラフの大部分を占める色。白や薄いグレーなど、他の色を邪魔しない無彩色がおすすめです。
メインカラー (25%): グラフの主要な要素に使われる色。企業のロゴカラーや、伝えたい内容のイメージに合った色を選びます。
アクセントカラー (5%): 特に強調したい部分に使う、目を引く色。メインカラーの反対色など、コントラストがはっきりした色を選ぶと効果的です。
この「70:25:5」の比率を意識するだけで、バランスの取れた見やすいグラフになります。
ルール2:色の持つイメージを理解して選ぶ
色にはそれぞれ、人が無意識に感じるイメージがあります。これを活用することで、より直感的に内容を伝えられます。
暖色系 (赤、オレンジ、黄など): 情熱、活気、注意、ポジティブな印象を与えます。売上目標の達成や、ポジティブな変化を示すデータに適しています。
寒色系 (青、水色、青緑など): 冷静、信頼、知的、落ち着いた印象を与えます。客観的なデータや、安定した推移を示すのに向いています。
中性色 (緑、紫、グレーなど): 安心、中立、穏やかな印象を与えます。他の色と組み合わせやすく、バランスを取るのに役立ちます。
伝えたいメッセージに合わせて色を選ぶことが、伝わるグラフへの第一歩です。
ルール3:情報の種類に合わせて色を使い分ける
グラフで扱うデータには、カテゴリーを区別するための「質的データ」と、数値の大小を表す「量的データ」があります。これに応じて色の使い方を変えることが重要です。
質的データ(例:商品A, B, C): それぞれが独立したカテゴリーなので、赤・青・緑など、色相(色合い)が異なる色を使って明確に区別します。
量的データ(例:満足度 低・中・高): データの大小や段階を表すため、同じ色相で明度や彩度(明るさや鮮やかさ)が異なる色(グラデーション)を使います。これにより、データの連続性が視覚的に分かりやすくなります。
【実践編】グラフの種類別・配色のコツ
基本的なルールを理解したら、次はグラフの種類ごとに具体的な配色のコツを見ていきましょう。
棒グラフ・円グラフ:カテゴリーの違いを明確に
複数の項目を比較する棒グラフや円グラフでは、各項目がはっきりと区別できることが大切です。
隣り合う要素には、色相差が大きく、かつ明度差もある色を選びましょう。同じような色合いが続くと、境界が曖昧になり見づらくなってしまいます。
折れ線グラフ:系列の区別としなやかな色のつながり
時間の経過とともにデータの推移を示す折れ線グラフでは、複数の系列が重なっても見分けられるように、それぞれの線の色を明確に変える必要があります。ただし、あまりに派手な色ばかりを使うと目がチカチカしてしまうため、全体のトーンを合わせつつ、彩度や明度を調整するのがおすすめです。
散布図:データのグループ分けを視覚的に
2つのデータの関係性を見る散布図では、プロット(点)の色でグループ分けを表現することがよくあります。グループごとに明確に異なる色を使い、どの点がどのグループに属するのかを一目で分かるようにしましょう。
【要注意】やってはいけない!NGな色の使い方
良かれと思ってやったことが、逆にグラフを分かりにくくしてしまうケースもあります。よくある失敗例を知っておきましょう。
意味のない多色使いは情報を混乱させる 😨
カラフルなほうが見栄えが良いと思いがちですが、色数が多すぎると、どこが重要なのか分からなくなり、かえって情報が散らかってしまいます。使う色は、前述の通り3色を基本とし、多くても5〜6色程度に抑えましょう。コントラストが低くて見えない 😑
背景色と文字やグラフの色が似ていると、コントラストが低く、非常に見づらくなります。特に、プロジェクターで投影する際は、画面で見るよりも色が薄く見えることが多いので注意が必要です。白背景には濃い色、濃い背景には明るい色を組み合わせるのが基本です。目がチカチカする色の組み合わせ 😵
彩度の高い色同士(例:純色の赤と青)を組み合わせると、境界線がチラついて見える「ハレーション」という現象が起き、見る人に不快感を与えます。どちらかの色の彩度を下げるか、間に白や黒の境界線を入れると改善できます。
すべての人に見やすく。カラーユニバーサルデザイン(CUD)を意識しよう
色の見え方には個人差があります。日本人男性の約20人に1人、女性の約500人に1人は、特定の色を区別しにくいとされています。そのため、誰もが情報を見分けられるように配慮された「カラーユニ-バーサルデザイン(CUD)」を意識することが非常に重要です。
CUDのポイントは、色だけに頼らずに情報を伝えることです。
色だけでなく、形や模様、線の種類を変える
例えば、折れ線グラフなら実線と破線を組み合わせたり、棒グラフに模様(ストライプやドット)を入れたりすることで、色の違いが分からなくても系列を区別できます。凡例だけでなく、グラフ要素の近くに直接ラベルを記入する
グラフの要素の近くに直接データ名や数値を書き込むことで、色を見分けなくても内容を理解できます。
【時短テク】配色ツールでセンスいらずのグラフ作成
「ルールは分かったけど、自分で配色を考えるのはやっぱり難しい…」という方は、便利なツールを活用しましょう!
おすすめの配色ツール
Web上には、美しい配色パターンを自動で生成してくれるツールがたくさんあります。
Adobe Color: Adobeが提供するプロ向けの配色ツール。様々なルールに基づいて調和のとれた色の組み合わせを提案してくれます。
Coolors: スペースキーを押すだけで次々とおしゃれな配色が生成される、直感的で使いやすいツールです。
xGrapherなら豊富なカラーパレットで簡単におしゃれなグラフが作れる
配色を考える時間がない、もっと手軽に美しいグラフを作りたい!という方には、当サイトのxGrapherがおすすめです。
xGrapherには、プロのデザイナーが監修した美しいカラーパレットが豊富に用意されているため、グラフの種類や用途に合わせて選ぶだけで、誰でも簡単に見栄えの良いグラフを作成できます。もちろん、カラーユニバーサルデザインに配慮した配色パターンも搭載。
データのCSVファイルをアップロードするだけで、あとは好きなデザインテンプレートとカラーパレットを選ぶだけ。面倒な色の設定に悩むことなく、本質的なデータ分析や資料作成に集中できます。ぜひ一度お試しください!
まとめ:色を味方につけて、伝わるグラフを作成しよう
今回は、グラフの色選びについて、基本的なルールから実践的なコツまで解説しました。
配色の基本は「3色」
色のイメージとデータの種類を意識する
NGな使い方を避ける
カラーユニバーサルデザインを心がける
これらのポイントを押さえるだけで、あなたの作るグラフは格段に分かりやすく、説得力のあるものになるはずです。
まずはこの記事で紹介したテクニックを一つでも取り入れて、ぜひxGrapherで実践してみてください。色を味方につけて、見る人の心に響くグラフを作成しましょう! 📊✨
よくある質問(Q&A)
Q1: グラフに使う色は多ければ多いほど良いですか?
A1: いいえ、逆効果になることが多いです。色数が多いと情報が散乱し、どこが重要なのか分からなくなります。基本は3色(ベース、メイン、アクセント)に絞り、多くても5〜6色程度に抑えるのが、見やすいグラフを作るコツです。
Q2: 白黒で印刷しても分かりやすいグラフにするにはどうすればいいですか?
A2: 色だけに頼らない工夫が必要です。例えば、棒グラフであれば模様(斜線やドットなど)で違いを表現したり、折れ線グラフであれば線の種類(実線、破線、点線など)を変えたりすることで、白黒でも各項目を明確に区別できます。
Q3: 会社のブランドカラーを使いたいのですが、見づらくなってしまいます。
A3: ブランドカラーをメインカラーやアクセントカラーとして使いつつ、その色の明度や彩度を調整した色を組み合わせるのがおすすめです。また、背景色とのコントラストを確保できる、白や薄いグレーといった無彩色のベースカラーと組み合わせると、ブランドイメージを保ちつつ見やすさも確保できます。
Q4: 強調したい部分が2つある場合、アクセントカラーも2色使って良いですか?
A4: はい、問題ありません。ただし、その2つの情報が同程度の重要性を持つ場合に限ります。もし重要度に差があるなら、より目立たせたい方に彩度の高い色を使い、もう一方は少し落ち着いた色にするなど、アクセントカラー内でも強弱をつけると、さらに意図が伝わりやすくなります。
Q5: センスの良い配色パターンを簡単に見つける方法はありますか?
A5: 「Coolors」や「Adobe Color」といったオンラインの配色ツールを使うと、おしゃれで調和の取れた色の組み合わせを簡単に見つけることができます。また、当サイトの「xGrapher」のように、あらかじめデザインされたカラーパレットが用意されているツールを利用するのも非常に効率的でおすすめです。
)
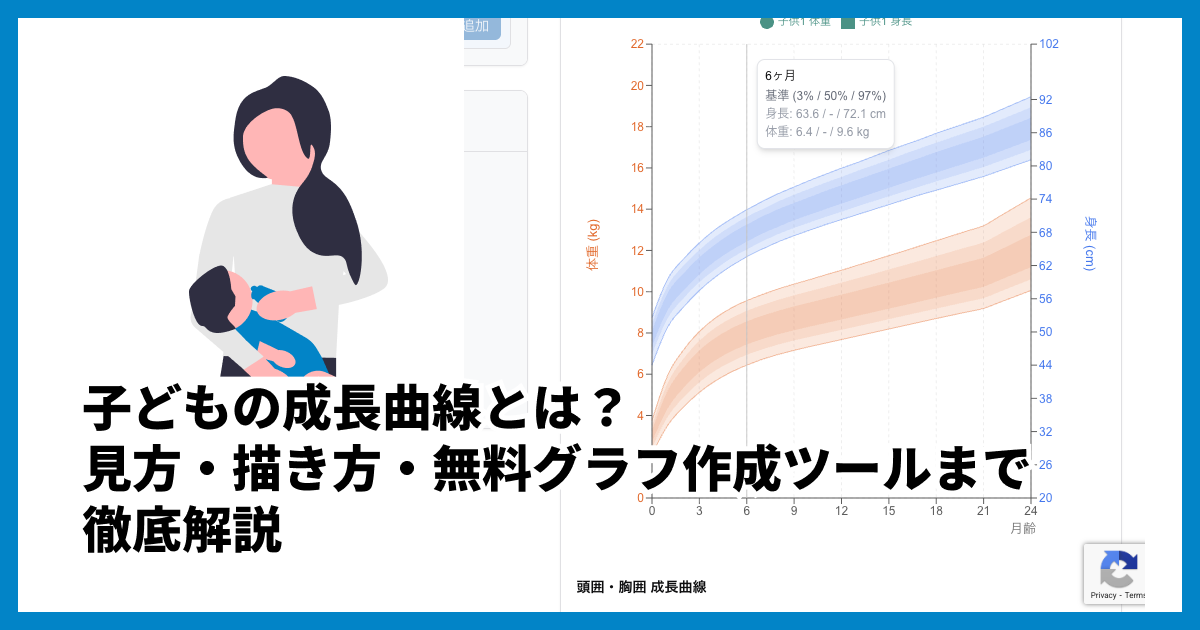)
)
)
)
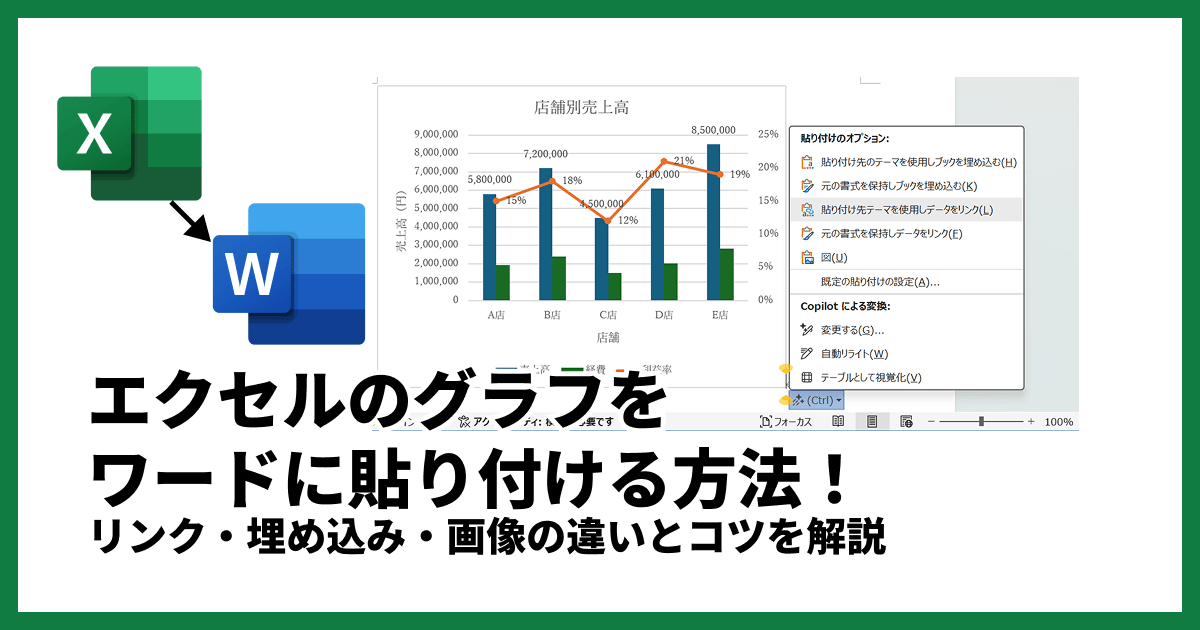)
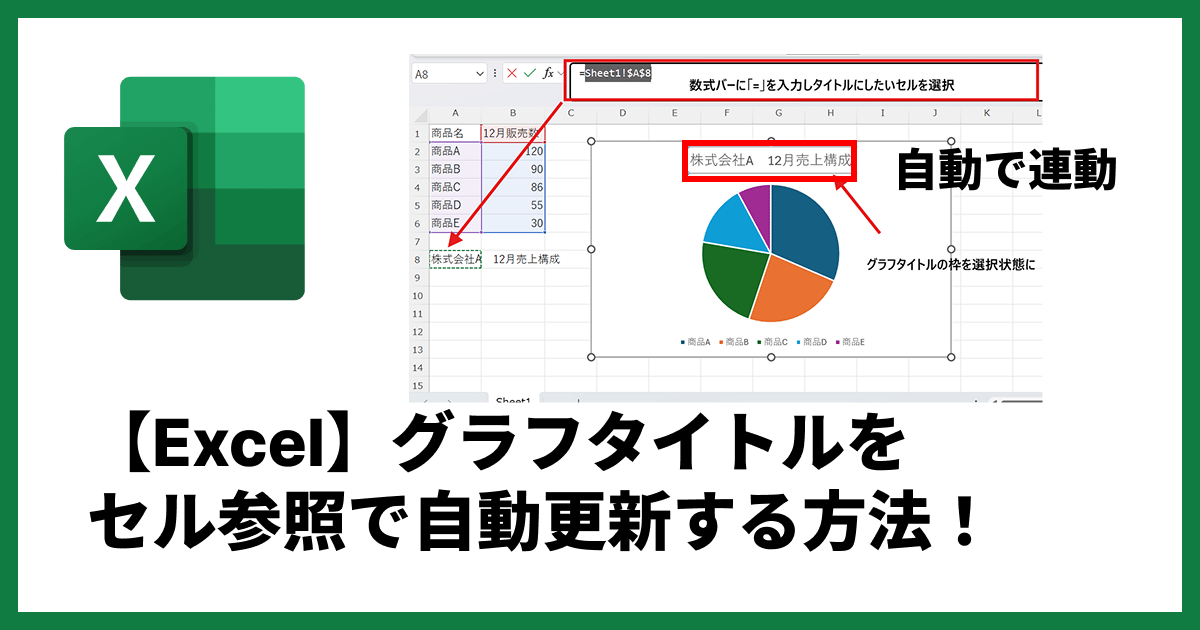)
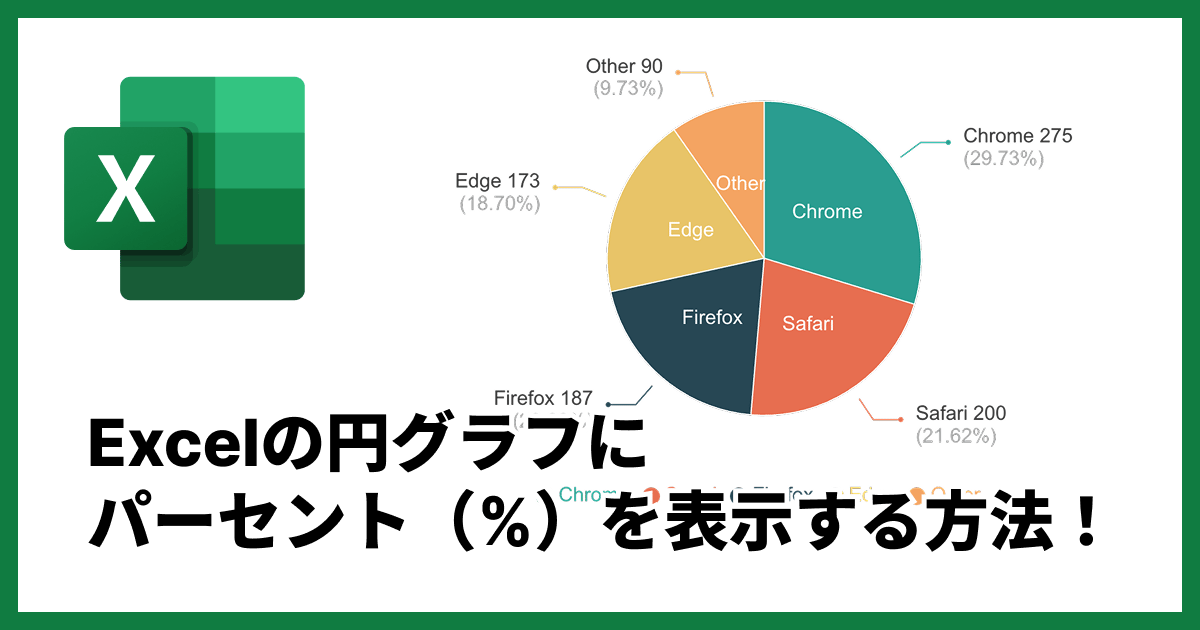)
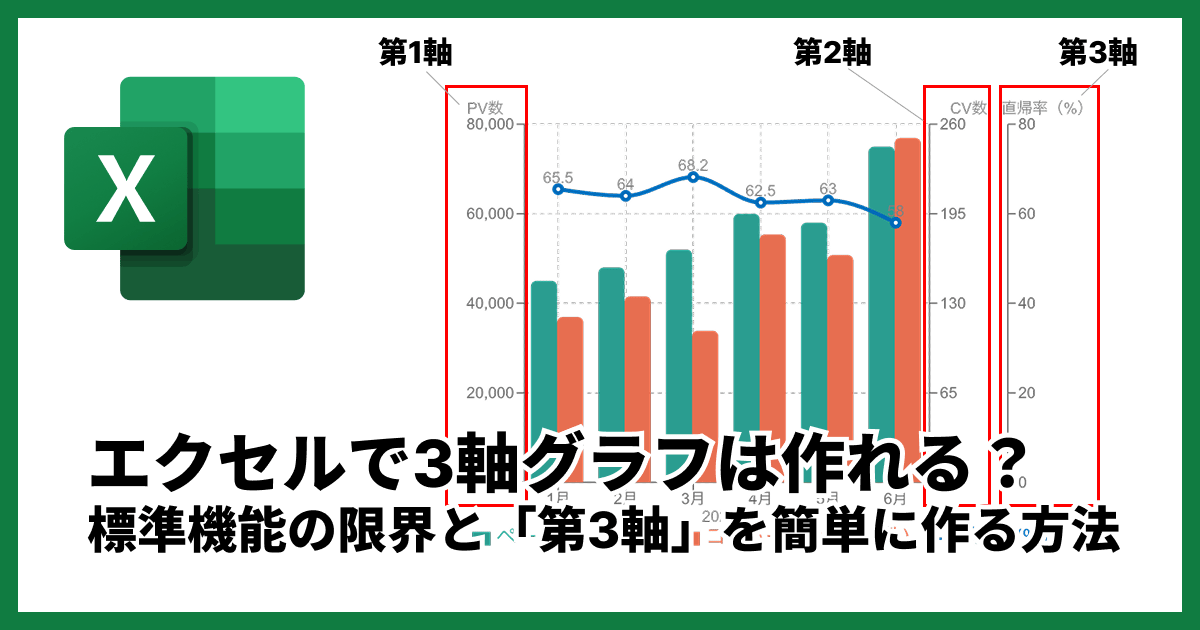)
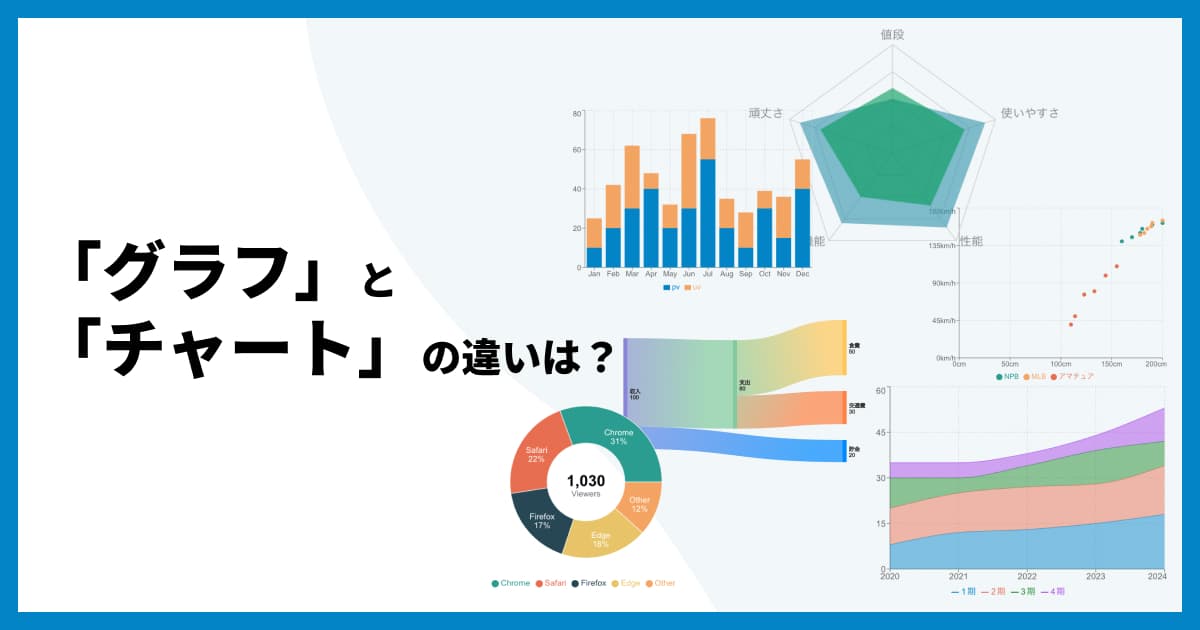)
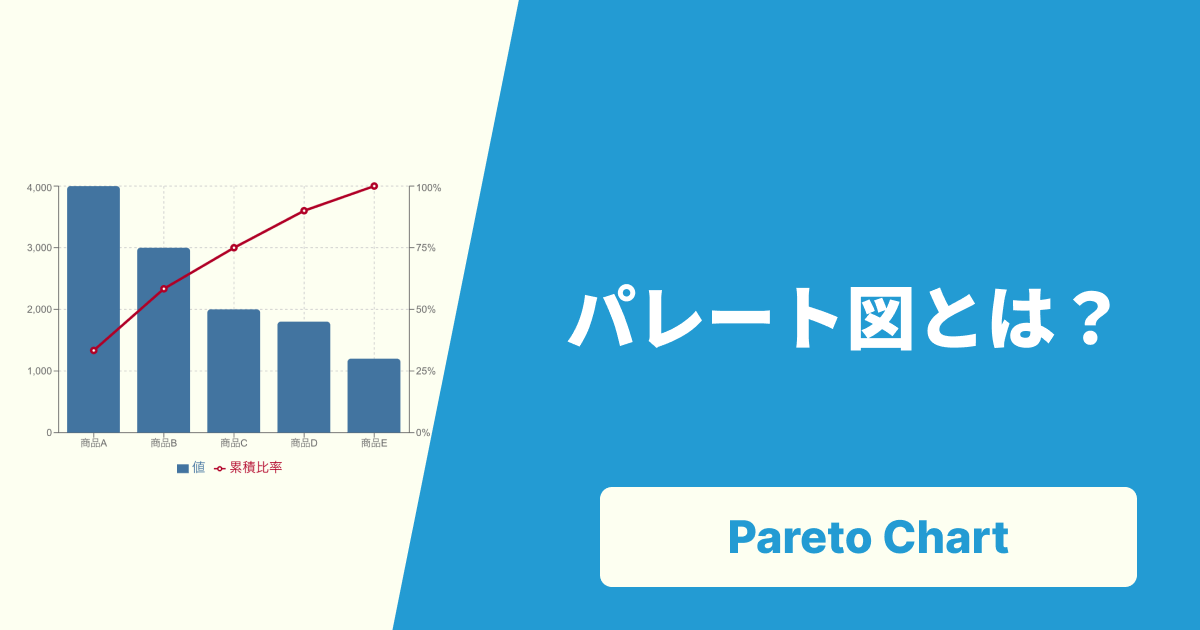)